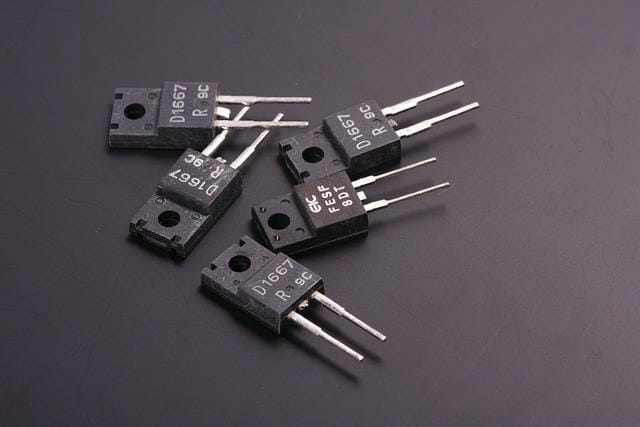組織がITインフラを運用していくうえで、外部からの様々な脅威は年々多様化している。サイバー攻撃による情報漏洩や業務停止のリスクは拡大し続けており、そのなかで高度な防御体制の構築が必須となった。この状況に脅威からIT資産を守るために存在するのが、いわゆる監視・運用部門である。この部門は、ネットワーク全体や接続されている多様なデバイスに対して一元的な監視・管理を実施し、未然にインシデントを察知し、適切な対応を取る役割を担っている。日々組織のネットワークにはパソコンだけでなく、スマートフォンやタブレット、IoT機器といった多種多様なデバイスが接続されている。
それぞれの端末やネットワーク機器が正常に稼働し、業務に支障をきたさないよう、かつセキュリティ脅威に対する監視を行うには専門的な知識とノウハウが不可欠となる。特に、社外へ持ち出される端末や遠隔拠点からのアクセスなどによって、ネットワーク境界が曖昧になっている現状では、包括的な視点での監視体制が強く求められている。具体的な運用としては、ネットワーク上を流れる通信データやイベントログの取得・分析を行い、不審な挙動や異常なトラフィックが存在しないかを24時間体制でチェックしている。また、ウイルス感染や予期しない通信の発生、内部不正など様々なリスクがあり得るため、各種セキュリティツールや自動化システムを活用して監視網を強化することも大切である。不審なアクティビティ発見時には、その原因特定から影響範囲の特定、阻止・隔離、復旧措置まで幅広い対応プロセスを実施している。
ネットワークを流れる膨大な量のデータをリアルタイムで監視するためには、専門のシステム人員だけでなく、AIや機械学習を活用したセキュリティ監視ツールの導入が浸透している。多様なデバイスの発するログを一括して収集・解析し、正常と異常、既知のサイバー攻撃手法と未知の脅威の検出を精緻に行う。このような体制によって、仮にゼロデイ攻撃など新しい手口で組織が狙われた場合でも、被害拡大前に禁止措置や警告発出など最適なアクションを素早く実行できる。また、全てのデバイスが物理的に同じ拠点に存在していないことがあたりまえとなった今、ネットワーク越しの遠隔監視は不可欠である。従来のようなオフィス中心の運用体制だけでなく、在宅勤務や出張者が利用するデバイスも同様のレベルで監視が可能でなければ、安全性は確保できない。
このため、VPNのような通信を暗号化する仕組みや、リモートアクセス端末の挙動解析などもあわせて行われ、抜け穴を徹底して狭めている。情報セキュリティ体制の強化という観点では、人の教育や啓発活動も重要だが、専門知識をもった担当者がネットワークおよびすべてのデバイスを常時監督することは、被害を未然に防ぐうえで決定的な意義を持つ。端末の設定ミスや稼働異常、不要なアプリケーションの使用、個人管理のパスワードによるアクセスといった内部要因に対しても細かな監視を行い、適時是正指示や警告をあげ、速やかな対応を実現する。この体制を維持運用するために不可欠なのは、インシデント発生時の迅速な連携である。ネットワーク上の不正アクセス兆候やデバイスの異常を検知した際には、担当者から経営層、関係各部署までが情報を共有し、時には外部のセキュリティベンダーや法的機関と連携しながら、最短かつ最適な措置が講じられる。
こうした体制高度化の基盤となっているのが、運用部門の存在だ。セキュリティ事象の一括管理を実現し、どこにいても組織の安全性を確保する縁の下の力として評価されている。もはやITシステムやデジタル機器の導入だけでは安全対策として不十分と言える現代では、不断の技術刷新と先端ツールの取り込み、現実の攻撃トレンドを網羅する知見の集積が日々求められている。運用部門が有している体系的な監視・対応プロセスや、増えつづけるデバイス・ネットワークを的確に管理する体制なくして、重大インシデントの回避や業務の安定維持は現実的ではない。今後も情報システムは進化し、ネットワークにつながるデバイスは増加の一途をたどることが確実である。
これら全体を俯瞰し可視化する力、そのなかで一つひとつの脅威を見逃さず最適な防御策を構築する知識と技能への要求は高まっている。運用部門が果たす役割は、組織の継続的発展と安全・安心の基盤を守る上で不可欠なものとして、今後も発展が期待されている。ITインフラの運用においては、サイバー攻撃や内部不正など多様化・高度化する脅威に対応するため、組織は専門的な監視・運用部門の存在が不可欠となっている。ネットワークにはパソコンだけでなく、スマートフォンやIoT機器など様々な端末が常時接続されており、それぞれを守るためには一元的で包括的な視点による監視体制が求められる。特に、社外持ち出し端末やリモートアクセスなどネットワークの境界が曖昧になる現状では、通信データやイベントログを24時間取得・分析し、不審な挙動をリアルタイムで検知・対応する仕組みが必要である。
AIや機械学習を活用したセキュリティツールや自動化による監視強化が普及し、未知の脅威への迅速な対応も可能となっている。また、在宅勤務や出張端末など物理的に多拠点に分散したデバイスも同等のレベルで監視され、VPNによる通信暗号化や遠隔挙動分析など、抜け穴の排除にも注力されている。運用部門は、設定ミスや内部不正、不要なアプリの利用など内部要因にも目を光らせ、是正指示や警告を通じて安全を確保し続けている。インシデント発生時には組織内外と迅速に連携し、最適な対応を講じて被害を最小限にとどめる体制も重要である。ITシステムの進化とともに監視・運用の高度化と知識の蓄積が求められ、今後も組織の安全と安定運用に不可欠な役割を担い続けることが期待されている。